昨年の大晦日に2024年を振り返るポストをしてから、物理的&精神的に忙しくて気づいたら半年以上ブログを更新できてませんでした。
何が忙しいって、東大で要求される勉強のレベルが私にとってはとても高いのですよ!
そんなわけで、時間さえあれば文献読んでるか勉強してるかで、自由に遊ぶ時間があまりありません。学生ってこんなに忙しかったんだと実感する毎日です。
とりたてて勉強が得意ではなかった人が東大に編入するとどうなるのかということを含め、東大生のリアルな勉強生活をここでお伝えしようと思います。
授業の予習が大変
私が通う東大文学部の授業は105分です。駒場の授業は基本90分なので、本郷とは時間割がちょっと違うという感じ。
105分の授業ってなかなか長いです。集中力も切れます。たまに、45分くらいで休憩を入れてくれる先生もいる。
授業が長いとどうなるかというと、単純に1週間やる範囲が広くなります。その分、予習復習も大変になるというわけです。
ただし、90分授業だからと言って予習復習が楽ということではありません。
4Sは駒場の授業を2コマ履修していたのですが、そのうちの一つは予習が多く、1週間で150ページくらいの論文や論考を読まなければいけませんでした。
昨年履修していた文学の授業は、長い作品だと1週間で300ページ超えということもありました。文学作品が好きな人にはなんてことない量なんだろうけど、私は普段あまり文学作品を読む習慣がないので結構ヘビー。
ノートが追いつかない
現代は板書の時代ではありません。ほとんどの先生がレジュメを映すか、ひたすらしゃべり、学生はPCやiPadでカタカタとノートをとるのです。
PCでノートをとるスタイルになるとどうなるかというと、先生が話すスピードが速い!
板書なら先生の板書スピードに応じて授業は進みますが、学生たちがPCでノートをとっている前提だと先生はひたすらしゃべるのです。
私は昨年のSセメスターはPCでノートをとっていたのですが、どうも頭に入らないのと、後でさっと見返したいときにいちいちファイルを開くのが面倒で、昨年のAセメスターからiPad+紙のノートというスタイルに変えました。
というわけで基本は紙のノートに書いているので、先生の話すスピードが速いと手が追いつかなくなりそうになる。それでも必死にひたすら書きます。
このノート速記訓練のおかげかわかりませんが、先日バイト先で「moniさんて文字書くの速いですよね」って言われました笑。
授業のレベルが高い
これがもっとも驚いたこと。授業のレベルが高いのでついていくのが大変。
マジで何言ってんのかわからない授業というのがあります。先生の言うことがわからないならまだしも、レジュメ発表した学生、授業中に発言した学生の言ってる内容が高度すぎて私の理解力では無理かも…ってことも。
このようなとき、「あぁここは東大なんだな」と実感します。
自分がいま東大生だから言うわけではなく、「世の中にこんなに賢い人っているんだな」ということを、東大にきてからよく感じています。
他大学から来られた非常勤の先生が、「この内容は難しいけど、東大生なら理解できるだろうと思うので説明します」と言っていたことがありました。先生も東大生ならこのくらいはわかるだろうと、高度なことを教えてくださるのですね。
レポートやレジュメ発表の負担
理系学部や他の学部に比べて、文学部は楽単なんでしょと思われてるかもしれません。
しかし、私にとっては文学部のレポート課題、レジュメ担当になったときの発表準備は時間がかかるものです。
文学部の期末評価はテストではなく、レポート提出であることが多いです。この事実を知ったとき、さすが文章を読ませる&書かせる学部だなと思いました。
レポート課題は4,000字以上という場合が多いですが、授業によっては6,000字以上を要求されたり、逆に2,000字程度という簡潔性を求められることもあります。
はじめは4,000字って結構書かせるなという印象だったのですが、レポートで設定する程度の主張をきちんと論証しようとすると、10,000字くらいは必要なんだなと思うようになりました。
そのことに気づけたのはよかったのですが、それと引き換えに各レポート作成に時間がかかっています。
レポート作成については、昨年の夏に購入したこちらの本にとてもお世話になってます!
私にとってレポートよりもさらに気が重たいのは、レジュメ作成担当になったときの準備です。
大教室の授業ではなく演習系の授業では、たいてい一人一度は発表がまわってきます。発表内容と形式は演習によりますが、スライドかレジュメによる発表が多いでしょう。
何か作品を読んで解釈を提示する、論考や論文を読んで要約する、外国語文献を読んで日本語訳と要約をするなど。
これらの発表で準備不足だった人、レジュメやスライドがお粗末だった人をほとんど見たことがありません。ここでも東大ってレベルたけーって思うわけです。
そんなわけで、自分がレジュメやスライドを準備するときも万全を期す必要があります。それでも万全ではないのですが、いい加減な状態では発表できないし、間違えたら恥ずかしいしという思いでできる限り労力と情熱を注ぎます。
おもしろそうな授業はできる限り受けてみたい、でも履修を増やすとレポートやレジュメ作成に追われることになる。
聴講(履修せずに授業に出席する、もちろん単位にはならない)という仕組みをうまく使えばいいのだろうけど、聴講だと結局行かなくなるのが人間の意志の弱さよね。
ちなみに美学芸術学専修は、原典講読を2年で4コマ履修しなければなりません。自分の担当時以外も外国語文献読んできてディスカッションに参加してね、みたいな授業もあるので原典講読はなかなかヘビーな科目の一つです。
東大の勉強生活は大変だけど刺激的
東大の勉強生活は思っていた以上に大変です。というか、私が思っていた以上に東大生がめちゃくちゃ賢いです。
「東大生はみんな賢く見える幻想ですよ」と言われたことがあるけど、幻想なんかじゃないと思う。
生まれて20年ちょっとで、どうやってそんな膨大な知識を得て、柔軟な思考力を構築したの?と思う人がたくさんいます。
周りのできる人と自分を比べてしまい、自分がいかに思考力や理解力が低いのかを痛感して憂鬱になりそうなときもありましたが、最近は周囲に賢い人がいるのは幸福なことなんだと思い始めました。
自分にはない視点、思考を持った人たちから毎日学ぶことができる。新しい知識や考え方をシェアしてもらえる。勉強のやり方そのものを教えてもらえる。
そして何よりも、勉強や研究に没頭し励んでいる関心分野の近い人たちと、思考を深めていくことができる環境があることに気づき、東大に入学して本当によかったなとしみじみ感じています。
東大での勉強生活はとても大変。だけどとても刺激的。
今は期末レポート作成に手がかかってるけど、それが終わったらこの夏は卒論に捧げます。
最後まで読んでくれてありがとう。
Hasta luegui!!!




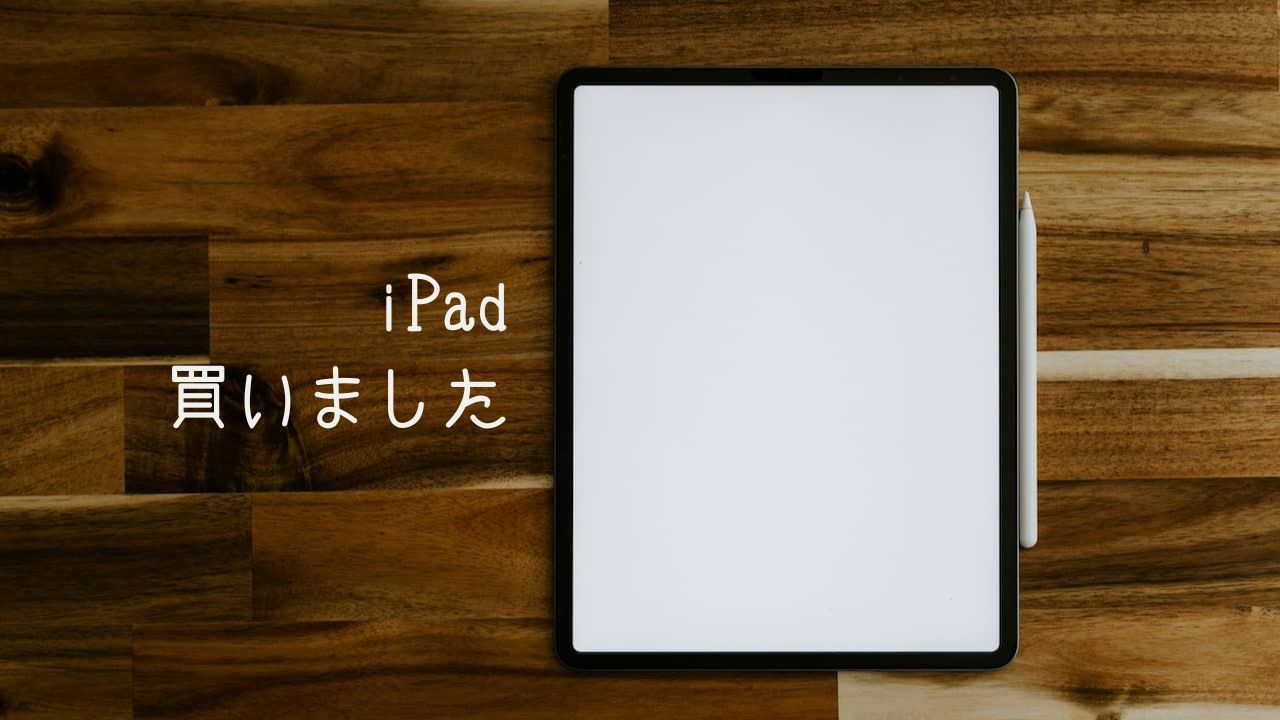
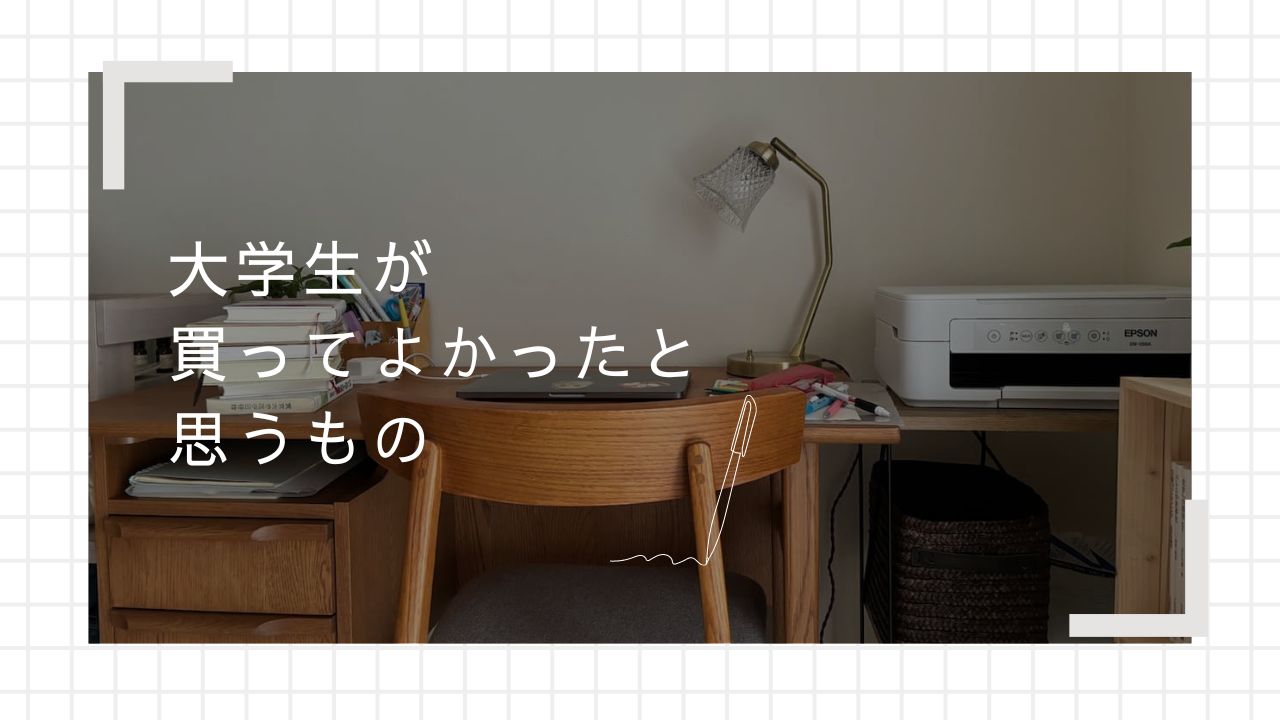


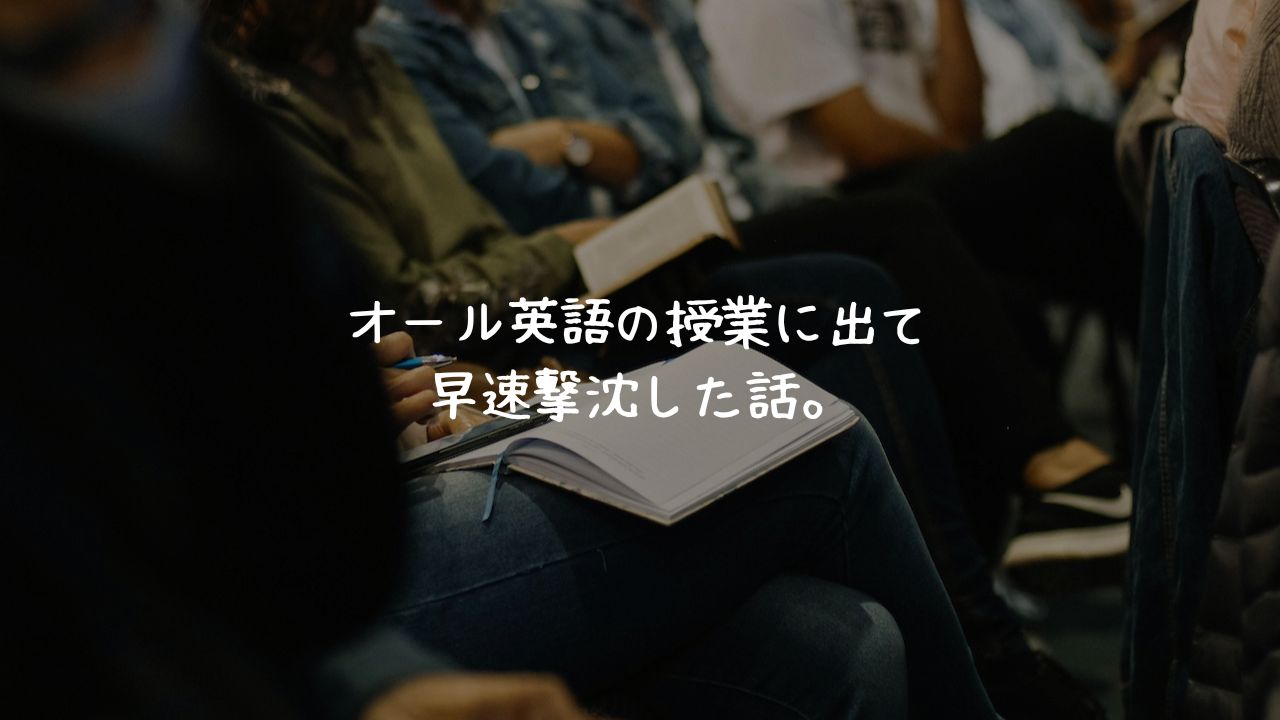
コメント