「踊り狂う」という言葉がありますが、踊りは人を狂乱させ、感覚を刺激し、ときに正常な判断を奪ったりします。
一遍上人の「踊り念仏」が全国的にブームを巻き起こしたという話を読んで、そういやウィーンでも人々がワルツを踊りすぎて会議が進まなかったみたいな話があったなと思い出しました。
時代も国も踊られる曲も異なるけど、踊りが人を狂わせたという意味では同じ。なんで人は踊りにそんなに夢中になるのでしょうか。
人を狂乱させた踊りについて、日本の盆踊り、ウィーンのワルツが人々を魅了した理由から、バブルの時代のお立ち台までを考えてみます。
一遍の踊り念仏の「宗教的エクスタシー」
先日、盆踊りを題材にしてある文章を書いていたのですが、その関連で読んだ盆踊りの本がなかなかに衝撃でおもしろかっったので、その内容をもとに踊りが民衆を狂乱に駆り立てた内容を見てみたいと思います。
その本は、「乱交」という視点から盆踊りの歴史を『万葉集』の時代にまでさかのぼって考察し、民俗文化は「性的共感こそが創り上げてきた」と主張するもの。その名も『盆踊り 乱交の民俗学』下川耿史、作品社。「乱交」と書かれるとかなりギョッとするかもしれませんが、そのマイナスなイメージも近年に作られたものなのだなということが本を読むとわかります。
この本の中で出てくるのが、一遍上人の踊り念仏の狂乱(第3章第1節)。そーいや日本史で「遊行上人」って習った気がする。下川さんの記述によれば、一遍は各地を行脚しながら法悦の境地に達する喜び、すなわち「宗教的エクスタシー」を庶民の前で見せることで、布教しようとしたのだという。
この「宗教的エクスタシー」というものは、なかなか際どい行為と一体であったそうで(詳細はぜひ本でお確かめください)、下品な行為として受け取られるものであった。「エクスタシー」と書かれていることから、性的な魅惑を含んだものと捉えられていたこともわかります。
踊り念仏が「宗教的エクスタシー」を庶民に体現させることで一遍の布教は成功。ものすごい額の寄付金が集まったようです。だからこそ一方で、はしたないとか下品だと批判も受けることになったということ。
法悦が境地に達することが、なぜ「宗教的エクスタシー」につながるのかについては、本に記載があるので詳しくは読んでほしいのですが、人々の狂乱の背景に奔放な性という側面があると考えると、今の時代ではない狂乱なのかなと思いました。現代では風紀委員が許さないでしょう。
この本を読むと、昔の日本は性に奔放だったんだなということがわかります。アダムとイブが裸だったことを恥ずかしいことだと気づいたように、外部からの目によってその「恥ずかしさ」のようなものに気づくのかもしれない。
ウィーン会議 会議は踊る、されど進まず
18世紀末のヨーゼフ2世の頃、ウイーンの街ではいたるところで音楽が鳴っていたそうで、街角やレストランで気軽に音楽を楽しむことができたのだそう。「食道楽の町」という側面もあり、陽気で快適な雰囲気が漂っていたようです。(加藤, 2003)
19世紀に入ると豪華なダンスホールがあらわれ、ウィーンの人口20万人に対して4分の1にあたる5万人が踊ることができるくらいの大小さまざまなホールがあった。当時、庶民に好んで踊られたのがワルツで、男女ペアでワルツは公序良俗を乱すとして禁止令が出ていたのみかかわらず、庶民たちはその陶酔感と解放感に興じたのだそう。この社会的な事象に伴って、ダンスホールが次々に建てられたということです。
このような状況下の1814年にウィーン会議は行われます。ロシア、フランス、イギリスなどの政治家たち、ナポレオン戦争後の欧州の秩序を取り戻すために集まったが、各国の利害関係の対立によって交渉は進まず、主宰国オーストリアによる派手な宴会や舞踏会が続けられたことからこの言葉が生まれたのです。
「会議は踊る、されど進まず」
実際に謝肉祭のシーズンに入ると、市民はダンスホールや居酒屋などで一晩中踊り明かしていたそうで、そのような市民の状況を『帝都ウィーンと列国会議 会議は踊る、されど進まず』の著者の幅さんは、「ダンス狂」「ダンス熱」と名付けている。(第六章)ウィーン市民の「ダンス熱」はものすごかったらしく、外国人の旅行記には
踊りすぎのため結核や心臓病で倒れるものが年間何万人にものぼる
妊娠八ヶ月でも女性はダンスをやめず、ホールには産室まで用意してある
(幅, 2000, pp. 320-321)
などの記載があったそう。また、ウィーンには「六時間以上踊らなければ満足できない者たちがわんさかといた」のだそうで、常軌を逸していることがよくわかります。まさに踊り狂っていたわけですね。
ウィーン会議が始まった当初、ワルツは庶民のダンスとみなされており、上流階級は主にお上品なメヌエットなどを嗜んでいたようです。舞踏会の最後、王侯貴族たちが退場するとワルツの演奏が始まり人々は待ってましたとばかりに生気あふれるワルツを踊るということ。それが徐々に、上流階級にも浸透していきます。ウィーン会議が終わる頃には、メヌエットに代わるものとしてワルツはヨーロッパ全土に広がりを見せていたようです。
なお、この頃のワルツは有名な「ウィンナ・ワルツ」ではなく、もう少しシンプルなワルツだったとのこと。ウィーンで公序良俗を乱すとされていたワルツは、当然海外でも批判されていたようで、イギリスの保守的な上流階級からは「ドイツ生まれの悪魔」と呼ばれていたらしい。
男女がペアになって回転しながら踊るということが秩序に反するということだったようだけど、風紀を乱す踊りが一方で、いやむしろそれだからこそ、人々を乱舞に駆り立てるのでしょうね。
そんなシンプルなワルツがあの優雅な「ウィンナ・ワルツ」に変化していったのは、1920年代頃です。「ウィンナ・ワルツ」誕生の経緯や二人の創始者、ランナーとシュトラウスの話は『ウィンナ・ワルツ ハプスブルク帝国の遺産』の第二章に詳しく書かれているので読んでいただきたいのですが、二人の人気っぷりはショパンがウィーンにやってきても注目されなかったと嘆いたほどのものだったようです。
ダンスホールでワルツに興じたウィーンの人々は、今度はランナーとシュトラウスが引き起こした「ウィンナ・ワルツ」の大ブームに湧くことになりました。加藤さんの記述を引用する孫引きになってしまうけど、音楽批評家のハンスリックが
「甘美に陶酔させる四分の三拍子のリズムが、頭から足までをとりこにし、偉大で真面目な音楽を圧倒してしまったのだ」(加藤, 2003)
と述べたのだそう。モーツァルトやベートーヴェンなどのウィーンで活躍した作曲家が影を潜めてしまうほど、市民は「ウィンナ・ワルツ」に熱狂し、とりこになっていたことがよくわかります。
ジュリアナ東京
以上の二つの人々を熱狂させた踊りに関する本を読んで、そういや最近でもそんな時代あったなと思い出したのが、「ジュリアナ東京」のお立ち台です。バブルの時代を象徴するダンスシーンですね。
広末涼子が出演していた『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』という映画でも出てきたと思うけど、逆立てた髪に派手なボディコン姿の女性たちが、扇子をひらひらさせながらお立ち台でデジタル音楽をバッグに踊るというやつです。
会社員だったとき、とても真面目そうなキャリアウーマンな先輩が「バブルの時代は定時に上がって六本木に行き、お立ち台で朝まで踊っていた」という話をしていて心底驚いた記憶があります。新卒の面接も今のような黒いスーツではなく、みんなカラースーツで受けていた時代らしいです。
バブルの時代、私はまだ小学生だったので大人の世界がどんなだったのかはわからないのですが、本当に万札でタクシー呼んだりしてたんですかね。そして、お立ち台で扇子片手に夜通し踊ってたんですかね!?
映画やニュースなどで当時の映像をちらっと見る限り、「ジュリアナ東京」のお立ち台もバブル時代の人々を熱狂させたのではないかと思います。髪を逆立て、ボディコンスタイルで扇子を持って踊るのが粋な時代だった。それがあっという間に消えてしまったと思うと、栄枯盛衰のようなものを感じます。
踊り狂う
私は昔から踊るのは割と好きです。今は機会もないのでほとんど踊らないけど、大学に入学してから身体で表現することを目的とした授業を受けたこともあります。
「踊り狂う」という経験はないかもしれません。小学生のときに槇原敬之の歌で何か踊ってたなとか、高校生のときにモーニング娘。をみんなでコピーしたなとか、ところどころ思い出すエピソードはあるのだけど、狂乱するほど踊った記憶はない。当時私が働いていたら、果たして「ジュリアナ東京」に踊りに行ったのだろうか?踊り狂っていたのだろうか?20代だったら行ったのかなぁ。
セビリアの春祭りで「セビジャーナス」を夜通し踊っていたのは、踊り狂っていた感覚に近かったかもしれない。カセタと呼ばれるテントの中は「セビジャーナス」しかかからないので、セビジャーナスタイム(みんなでセビジャーナス踊ろう的な時間)になれば、時にははじめましての人とペアで何ターンも「セビジャーナス」を踊っていた。
あれは一種の踊り狂いだったかもしれないな。みんながセビジャーナスの魔法にかかる一週間。

最後まで読んでくれてありがとう。
Hasta luegui!!!



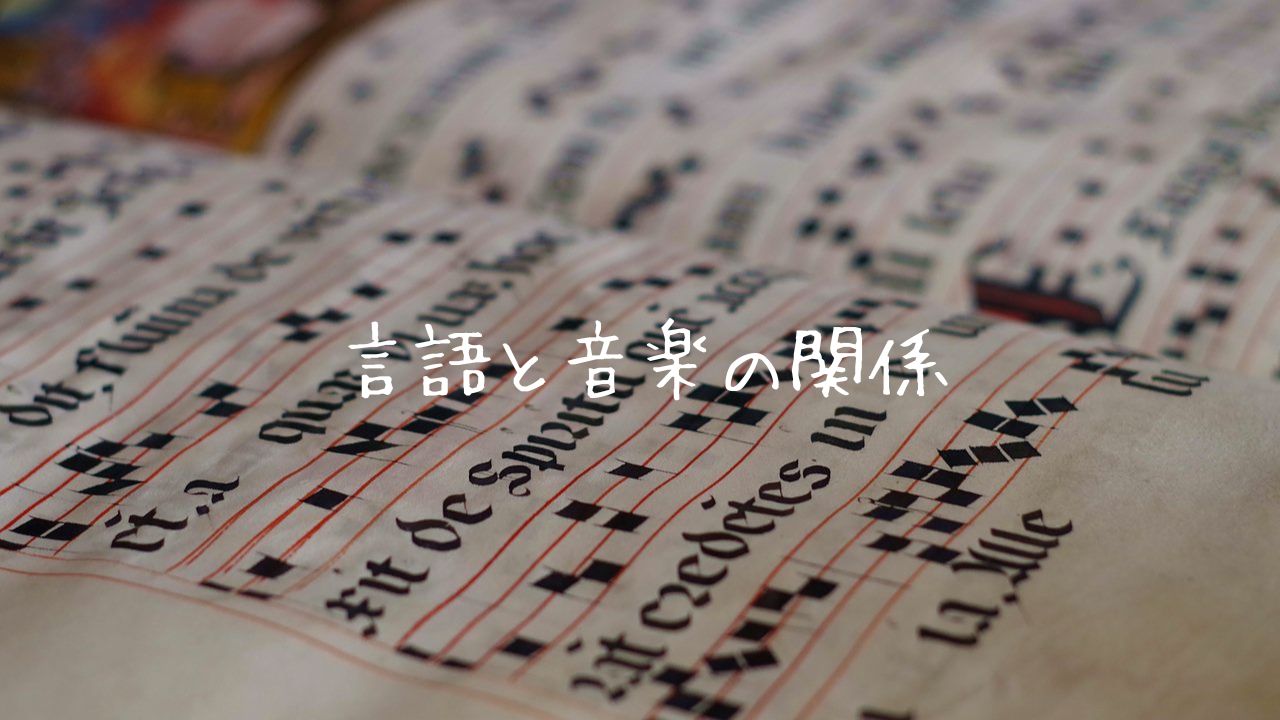


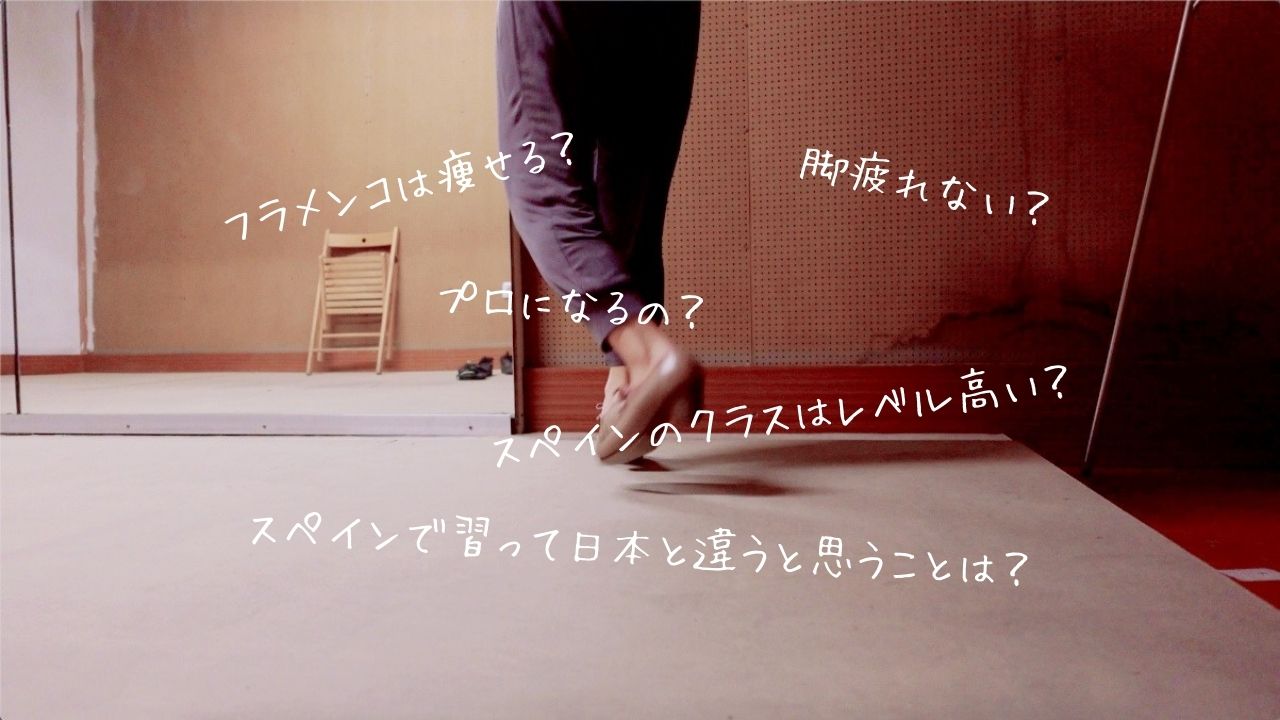


コメント